電子カルテの導入費用は高い?
どのサービスを選ぶべき?
このように悩む方は多いでしょう。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテのシェア率TOP3
電子カルテ市場は年々拡大し、多くの医療機関が導入を進めています。ここでは、国内シェア率TOP3の製品について、それぞれの特徴や強みを解説します。
1位 Medicom‐HRシリーズ:ウィーメックス株式会社(PCHグループ)

Medicom‐HRシリーズは、長年にわたり多くの医療機関に支持されている電子カルテです。豊富な導入実績と高い信頼性を誇り、診療所から大規模病院まで幅広く対応できる点が強みです。直感的な操作性や多機能性に加え、安定した稼働環境が評価されています。
さらに、PCHグループとしてのバックアップ体制も整っており、サポート力の高さが利用者から好評です。診療支援や経営分析など、医療機関の多様なニーズに応える機能が充実しているため、今後も高いシェアを維持することが見込まれています。
2位 Dynamics:株式会社ダイナミクス

Dynamicsは、クラウド型電子カルテの先駆け的存在として注目されています。オンプレミス型と比べて初期投資を抑えやすく、中小規模のクリニックに適している点が特徴です。リモート環境でもアクセスできる利便性やセキュリティ面の強化により、多くの医師から高い支持を得ています。
また、操作性のシンプルさも強みであり、スタッフの教育コストを軽減できます。バージョンアップや機能追加がスムーズに行える点もクラウド型ならではのメリットです。今後も医療DXの加速に伴い、さらなる導入拡大が期待されています。
3位 M3 Digikar:エムスリーデジカル株式会社

M3 Digikarは、医師専用ネットワーク「m3.com」を運営するエムスリーグループが提供する電子カルテです。そのため、最新の医療情報や製薬会社との連携に強みを持ち、診療効率化や情報収集をサポートします。業務フローに沿った使いやすい設計と、専門領域に対応する柔軟性が評価されています。
さらに、他システムとの連携性にも優れており、検査機器や会計システムとスムーズに統合可能です。特に診療所やクリニック向けに適した設計が多く、低コストでの導入が可能な点も魅力となっています。今後は医療情報プラットフォームとの統合により、さらに利便性が高まると考えられます。
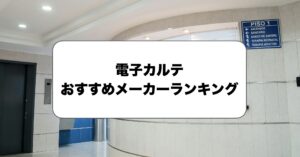
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
その他の人気の電子カルテサービス7選を比較!
電子カルテは、医療現場の効率化と情報共有の基盤として欠かせない存在です。ここでは、国内で高い人気を誇る電子カルテ10サービスについて、それぞれの特徴を紹介します。
富士通(HOPEシリーズ)

富士通のHOPEシリーズは、大規模病院から診療所まで幅広く対応できる電子カルテです。長年の実績に基づいた高い信頼性と豊富な導入事例を持ち、堅牢なセキュリティと柔軟なカスタマイズ性が特徴です。病院内のシステムと連携できる点も強みとされています。
さらに、クラウド対応のラインナップも提供しており、院内外での活用が可能です。医療業務全体を支援する設計により、診療効率化だけでなく経営改善にもつながります。そのため、医療機関の規模を問わず人気の高い製品です。
東芝テック(TOSMEC)
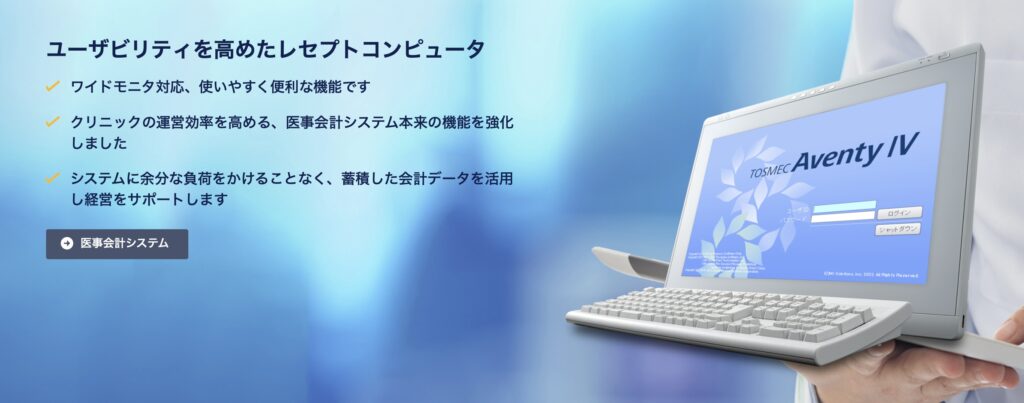
TOSMECは、使いやすさと安定性を重視した電子カルテとして知られています。特に診療所や中小病院で導入されることが多く、シンプルな操作性がスタッフから高く評価されています。医療現場のワークフローを意識した設計が強みです。
また、必要に応じて機能拡張ができる柔軟さも魅力です。電子カルテだけでなく周辺システムと連動し、スムーズな情報共有を実現します。導入コストを抑えつつ高い効果を発揮できる点が選ばれる理由です。
Qualis

大規模病院向けに強みを持つ電子カルテです。病院全体のシステム統合を目的としており、医療・会計・検査などを一元管理できます。大規模導入での実績が豊富で、高度なセキュリティ管理も整っています。
さらに、クラウドや地域医療ネットワークへの対応も可能で、外部とのデータ連携にも強い点が特徴です。医療連携の推進を支えるプラットフォームとして、多施設で採用されています。今後も地域医療連携の中心的役割を果たすことが期待されます。
CLINICS

CLINICSは、診療所や中小病院に特化した電子カルテです。直感的に操作できるUIが特徴で、医師やスタッフの負担を軽減します。業務効率化に加え、経営面のサポート機能も搭載しています。
クラウド対応によって、セキュリティを確保しつつ外部からのアクセスも可能です。多くの診療所で導入されている背景には、導入から運用までの安心サポート体制があります。特に小規模施設での評価が高い製品です。
CLIUS

CLIUSは、大規模医療機関での運用実績が豊富です。システムの安定性と高度な機能を兼ね備えており、病院全体の業務を支援します。特に情報管理やセキュリティに強みを持ちます。
また、カスタマイズ性が高く、各病院のニーズに応じた対応が可能です。導入から運用までのサポートも充実しており、信頼性の高いサービスとして認知されています。堅実な選択肢を求める医療機関に向いています。
SUPER CLINIC

SUPER CLINICは、医療と介護の両領域で活用できるシステムを提供しています。電子カルテに加えてナースコールシステムなどとの統合が可能で、現場の利便性を高めています。患者情報の一元管理が強みです。
医療と介護の架け橋として、情報連携をスムーズに行える点が評価されています。高齢化が進む日本において、医療・介護連携を重視する施設に適した選択肢といえます。将来的な需要拡大が期待される分野です。
ユヤマ(YUYAMA)
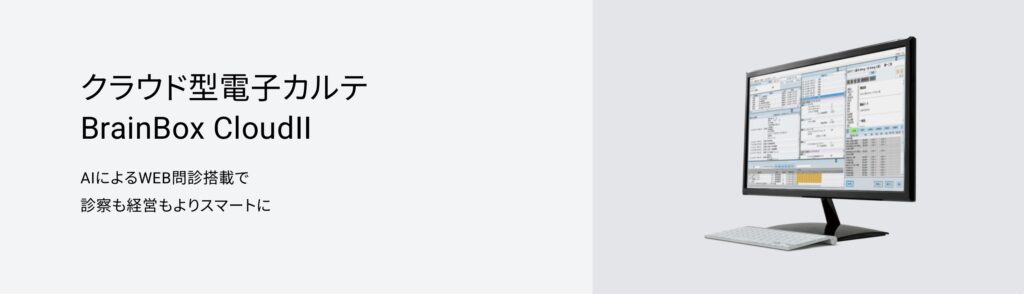
ユヤマは、調剤機器の大手メーカーとしての強みを活かした電子カルテを展開しています。調剤業務と連携できる点が特徴で、薬局やクリニックに適しています。業務効率化と安全性を両立させています。
また、直感的な操作性により、スタッフの負担軽減にも寄与します。調剤機器とのシームレスな統合はユヤマならではの強みで、薬剤管理の正確性を高めます。薬局を中心に今後も導入拡大が期待されています。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテの選び方は?
電子カルテは医療現場の効率化に直結するため、慎重な選定が必要です。ここでは、導入時に重視すべき4つのポイントについて詳しく解説します。
診療科や施設規模に合わせたサービスを選ぶ
電子カルテは、診療科や施設規模に適した機能を備えたものを選ぶことが重要です。大規模病院では部門間連携や高度なデータ管理が求められる一方、クリニックではシンプルで低コストなシステムが適しています。自院の診療体制に合った機能を持つ製品を検討することが必要です。
また、施設の将来像も考慮して選ぶことが大切です。診療科の拡大や患者数の増加を見据え、柔軟に機能追加や拡張が可能な製品を導入することで、長期的な運用コストを抑えることにつながります。
操作性が良いものを選ぶ
電子カルテは日常業務で頻繁に使用するため、直感的に操作できるUIを備えたものが望ましいです。複雑な操作が必要だと入力に時間がかかり、診療効率が低下してしまいます。操作性に優れた製品はスタッフの教育コストも抑えられます。
さらに、モバイル端末からのアクセスや音声入力など、利便性を高める機能を持つ製品も注目されています。現場の負担を軽減し、患者対応の質を高めるためには、使いやすさを最優先に考えることが大切です。
サポート体制と導入実績を確認する
電子カルテは導入後のサポートも欠かせません。トラブル時に迅速な対応をしてくれるサポート体制があるかを確認することが重要です。システム障害が長引くと診療に大きな影響を与えるため、安心して任せられる体制を選ぶ必要があります。
また、導入実績が豊富な製品は信頼性が高い傾向にあります。実績のあるサービスは医療現場の声を反映した改善が進んでおり、安心して利用できます。口コミや導入事例を調べることも有効です。
他システムとの連携性(レセコン・予約・会計)を確認する
電子カルテは単体で完結するものではなく、レセコンや予約システム、会計システムとの連携が不可欠です。連携が不十分だと、二重入力や情報の不整合が発生し、業務効率が大幅に低下してしまいます。
特に診療所では、患者の受付から会計までの流れを一元化できるかどうかが重要です。検査機器やオンライン診療システムともスムーズに接続できる製品を選ぶことで、業務効率化と患者満足度の向上を同時に実現できます。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテの価格・料金は?
電子カルテの導入には初期費用やランニングコストが発生します。費用の内訳やクラウド型とオンプレミス型の違いについて解説します。
初期導入費用の相場
電子カルテの初期導入費用は、一般的に50万~200万円程度が相場とされています。導入内容にはシステム本体だけでなく、周辺機器やサーバー、ネットワーク環境の整備費用も含まれます。そのため、施設の規模や必要な機能によって大きく変動します。
特にオンプレミス型では、サーバー設置やカスタマイズ費用がかかるため高額になりやすい傾向があります。一方でクラウド型は初期費用を抑えやすく、導入のハードルが低いのが特徴です。導入時には、自院に必要な機能と予算を明確にして検討することが重要です。
月額利用料や保守料金の目安
電子カルテは導入後も月額1万~5万円程度の利用料や保守料金が必要です。これにはシステム利用料のほか、サポートサービスやアップデート費用が含まれるケースが多いです。契約形態によっては追加費用が発生することもあります。
大規模病院の場合は、利用人数や機能追加によってさらに高額になる場合もあります。保守契約の範囲を確認し、サポート体制の充実度を重視することが安心につながります。ランニングコストを抑えるためには、必要最低限の機能を選定する工夫も必要です。
クラウド型とオンプレミス型の価格差について
クラウド型は初期費用が低く、月額利用料中心で運用できるのが特徴です。小規模クリニックや開業医に人気があり、導入スピードの速さもメリットとなっています。サーバー管理の手間もなく、比較的低コストで利用可能です。
一方、オンプレミス型は初期投資が大きくなるものの、長期的に見れば安定した運用が可能です。院内のカスタマイズ性が高く、大規模施設での採用が多く見られます。価格面だけでなく、施設の規模や運用体制に合った方式を選ぶことが大切です。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテをコストを抑えて導入する方法
電子カルテ導入は大きな投資ですが、工夫次第で費用を削減できます。ここでは、コストを抑えて導入するための具体的な方法を紹介します。
クラウドサービスを選ぶ
電子カルテを低コストで導入するなら、クラウド型サービスの活用が有効です。オンプレミス型のように高額なサーバーや専用機器を用意する必要がなく、初期費用を大幅に削減できます。また、アップデートや保守もサービス提供側が行うため、維持管理コストも抑えられます。
さらに、クラウド型は導入スピードが早く、スモールスタートに適しています。小規模クリニックや新規開業医に特に人気があり、必要な機能を月額利用料で使える点も魅力です。将来的な規模拡大にも柔軟に対応できるのが強みといえます。
中古端末・既存機器を活用する
電子カルテ導入では、新品機器をすべて揃える必要はありません。既存のPCや周辺機器を活用すれば、導入コストを大幅に削減できます。特にクリニックでは、既存のレセコンやプリンターをそのまま利用できる場合も多くあります。
また、中古端末を活用することも選択肢のひとつです。信頼できるベンダーから購入すれば、十分に実用可能であり、初期投資を抑える効果が期待できます。導入計画時に既存資産の有効活用を検討することで、無駄な支出を防ぐことができます。
補助金・助成金を利用する
電子カルテの導入には、補助金や助成金の活用が非常に有効です。代表的な制度には「IT導入補助金」や「業務改善助成金」があり、導入費用の一部を負担してもらえます。これにより、自己負担額を大幅に軽減することが可能です。
さらに、地域医師会や自治体による独自の助成制度が設けられている場合もあります。事前に調査して申請準備を整えることが重要です。補助金を上手に活用することで、コストを抑えつつ最新のシステムを導入できるチャンスが広がります。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテ導入に利用できる補助金
電子カルテの導入は費用負担が大きいため、補助金の活用が効果的です。ここでは、医療機関が利用できる代表的な補助金制度を紹介します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、電子カルテを含むITツール導入に広く利用できる制度です。対象となるサービスを導入した場合、費用の一部を国が補助します。診療所や小規模病院がコストを抑えて最新システムを導入するのに役立ちます。
申請には事前にITベンダーの登録が必要であり、採択には事業計画の提出も求められます。補助率や上限額は年度によって異なるため、最新情報を確認しながら計画的に活用することが重要です。
医療機関向け地域医療介護総合確保基金
この基金は、地域医療や介護体制の充実を目的とした支援制度です。電子カルテ導入も対象となり、地域医療連携や医療体制の強化に寄与する取り組みを支援します。特に中小規模の病院や診療所で活用が進んでいます。
都道府県が窓口となり、申請から実行まで地域ごとに運用されています。地域包括ケアシステムの一環として位置づけられており、長期的な医療体制の改善を目指す場合に適した補助金です。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、診療所など小規模医療機関にも利用可能な制度です。本来は中小企業向けの経営支援策ですが、医療機関が対象となるケースもあります。電子カルテ導入を通じた業務効率化や患者サービス向上が評価されます。
申請には商工会議所などのサポートが活用できるため、初めての申請でも比較的取り組みやすい制度です。補助率は高くないものの、導入コストの一部を軽減できる点で有効な選択肢となります。
業務改善助成金
業務改善助成金は、労働環境改善や生産性向上を目的とした助成制度です。電子カルテを導入することでスタッフの負担軽減や労働時間の短縮につながる場合、対象経費として認められる可能性があります。
特に長時間労働の是正や業務効率化を重視する医療機関に適しています。助成額は導入費用の一部に限定されますが、人材確保や職場環境改善と合わせて効果的に活用できます。費用対効果を考えた導入を後押しする制度です。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテを導入するメリット
電子カルテの導入は医療現場の効率化だけでなく、患者サービスや経営改善にも大きな効果をもたらします。ここでは、導入による代表的な4つのメリットを解説します。
業務効率化と医療の質向上に繋がる
電子カルテを導入することで、診療記録の入力や検索が迅速に行えるようになり、業務効率が大幅に向上します。紙カルテに比べて記載の手間が減り、診療時間を患者対応に充てられるようになる点が大きなメリットです。
また、検査結果や処方履歴をすぐに参照できるため、診療の精度やスピードが向上します。医療従事者間で情報を共有しやすくなることで、医療の質を底上げし、安全性の高い診療を実現できます。
患者データの一元管理と共有ができる
電子カルテは、患者データを一元的に管理し、複数部門で共有できる仕組みを提供します。診療科をまたぐ情報の確認や、検査データとの連携がスムーズになり、患者対応の重複やミスを防止します。
さらに、紹介状や地域医療ネットワークとの連携も容易になり、他医療機関との情報共有が効率的に進みます。患者にとっても、より一貫性のある医療サービスを受けられるという安心感につながります。
遠隔医療やクラウド活用の推進ができる
近年注目されている遠隔医療やクラウド型サービスの基盤となるのが電子カルテです。自宅や別拠点からでもデータにアクセスできるため、在宅診療や地域連携を進める上で欠かせない存在です。
また、クラウドを活用することで常に最新バージョンを利用でき、セキュリティ対策も強化されます。デジタル技術を活かした医療の推進に不可欠であり、今後さらに重要性が高まると考えられます。
コスト削減と経営改善効果が期待できる
電子カルテは、紙カルテの保管コストや事務作業の削減に直結するため、経営面でも大きな効果があります。紙の使用や保管スペースの縮小により、物理的コストを抑えることができます。
さらに、診療データを活用した経営分析が可能になり、収益構造の改善にもつながります。業務の効率化と経営改善を同時に実現できるため、医療機関にとって長期的な投資価値の高いシステムといえます。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテを導入するデメリット
電子カルテは便利な一方で、導入や運用には課題も存在します。ここでは、医療機関が直面しやすい代表的なデメリットを解説します。
初期導入費用や維持コストが高額
電子カルテは、初期導入費用が数十万~数百万円にのぼる場合があり、維持費も継続的に発生します。小規模クリニックや新規開業医にとっては大きな負担となるケースが少なくありません。特にオンプレミス型は高額投資が必要です。
さらに、保守契約やバージョンアップに伴う追加コストも考慮しなければなりません。クラウド型を選択すれば初期費用を抑えられるものの、毎月の利用料は固定的に発生します。長期的なランニングコストを見据えて導入を判断する必要があります。
システム障害・セキュリティリスク
電子カルテはデジタル管理であるため、システム障害やサイバー攻撃などのセキュリティリスクが存在します。障害発生時には診療が滞る可能性があり、患者対応に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
セキュリティ対策を強化することは必須であり、クラウド型の場合もベンダー側の管理体制を確認する必要があります。バックアップ体制や障害時の代替手段を整備しておかないと、医療現場の信頼性が損なわれる可能性があります。
スタッフ教育や習熟に時間がかかる
新しい電子カルテを導入すると、医師やスタッフに操作方法を習得してもらう必要があり、教育や研修に時間がかかる点がデメリットです。慣れるまでは入力に時間がかかり、診療効率が一時的に低下する可能性もあります。
また、医療従事者のITスキルには差があるため、習熟度によって業務にばらつきが生じる場合もあります。導入前に十分なトレーニング期間を設け、サポート体制を整えることがスムーズな定着のカギとなります。
導入後の運用体制が必要
電子カルテは導入して終わりではなく、運用を安定させるための体制整備が不可欠です。システム更新やトラブル対応を行うため、担当スタッフや外部ベンダーとの連携が欠かせません。これが医療機関にとって新たな負担となる場合があります。
さらに、診療スタイルや業務フローに合わせて継続的に改善を行う必要もあります。運用体制が整っていないと、システムを十分に活かせず投資効果が薄れてしまいます。導入前に長期的な運用計画を立てることが重要です。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
電子カルテの導入ならクリニック相談室へ!
これから電子カルテの導入をお考えの方は、クリニック相談室へご相談ください。
クリニック相談室では、複数メーカーへの一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。
どの製品を選べば良いか分からない方も、以下のリンクよりご相談いただければすぐさまぴったりのサービスが見つかります。
まずはお気軽にご相談ください。
電子カルテの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短で電子カルテを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
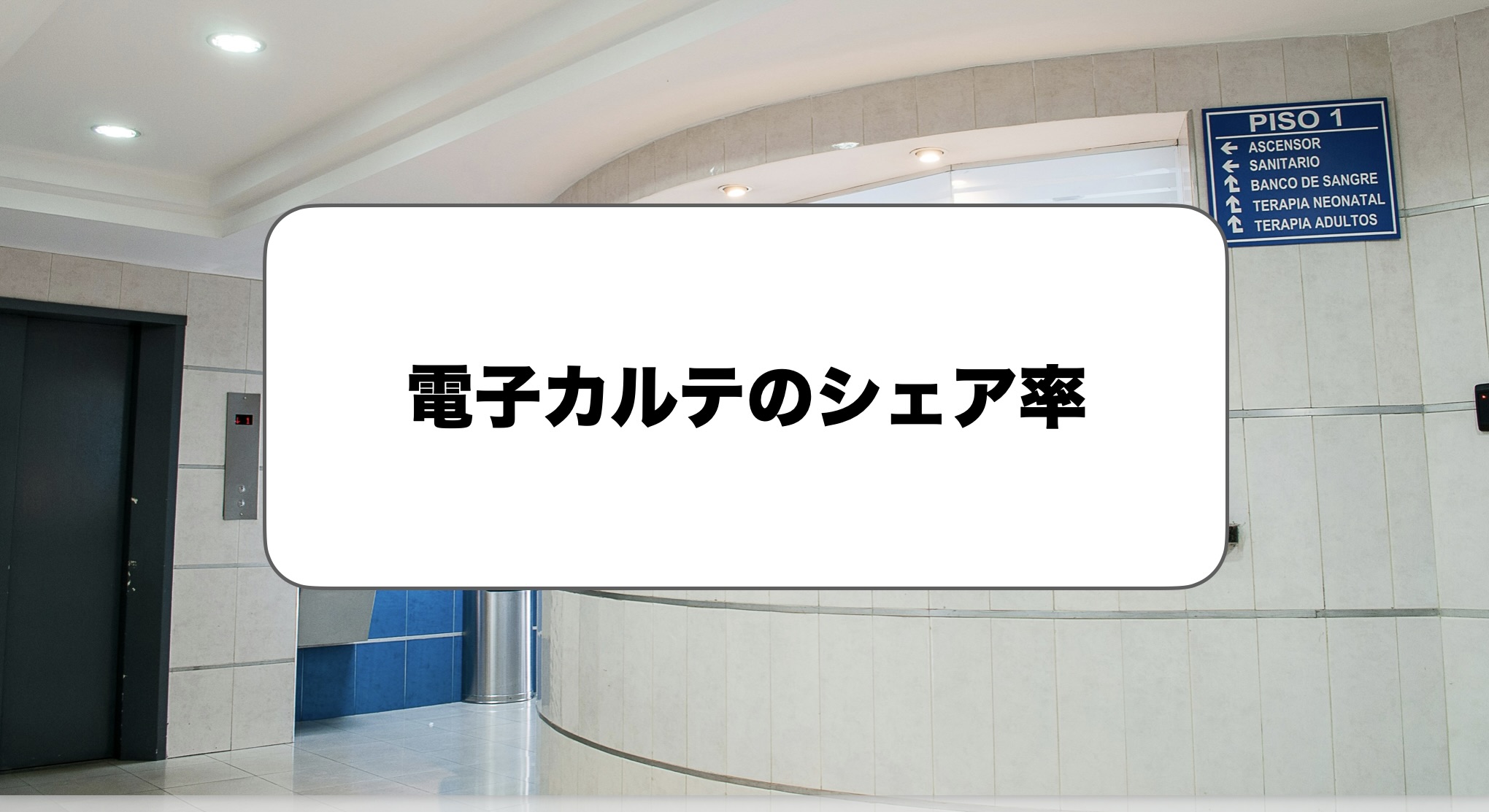
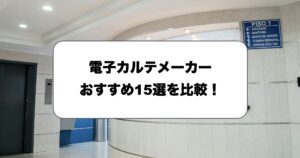
コメント